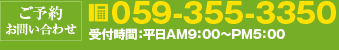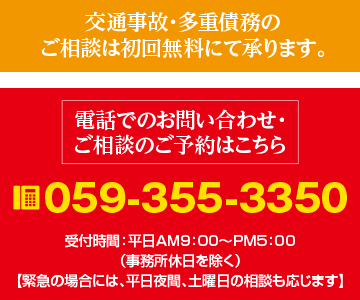建物建築紛争
 新築したマイホームに「瑕疵(かし)」が見つかった場合
新築したマイホームに「瑕疵(かし)」が見つかった場合
新築したマイホームに不具合事象、その原因である「瑕疵」が見つかった場合、
何をすべきかと言えば、メーカーや販売業者の責任を問うことになります。
時間が経過すると、責任追及もままなりません。
| 1. |
建物新築請負契約において、仕事の目的物に瑕疵がある場合の請負人の責任については、次のようになっています。
工事完成前には民法の一般規定である債務不履行責任を負い、工事完成後には債務不履行責任の適用は排除され、民法634条以下の瑕疵担保責任を負うことになります。
仕事完成後の請負人の瑕疵担保責任の存続期間(民法637条~639条)は、民法は、①木造建物または地盤の瑕疵は、引渡後5年間、②石造、土造、煉瓦造、金属造の建物は、引渡後10年間、③建物が瑕疵により滅失・毀損した場合、そのときから1年間と規定されています。
契約や約款において、「引渡の日から1年ないし2年」と短縮されるケースが多く、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款を用いた契約では、木造建物については引渡後1年、コンクリート造建物等や地盤については引渡後2年間に短縮されています(同約款27(2))。
|
| 2. |
例えば、建物完成・引渡後7年が経過しておれば、請負人の瑕疵担保責任の存続期間を超えているので、請負人の責任を問うことができません。
|
| 3. |
もっとも、工事が予定された最終の工程まで一応終了している場合に、新築住宅としての重要な部分が完全には施工されず、不完全で約旨に適っていないから不完全履行であるとした判例(横浜地判昭和50年5月23日判タ327.236)があります。
|
| 4. |
残された請負人の責任としては、民法709条の不法行為責任(建物引渡時から20年間存在します)です。これが問えるかは、「建物としての基本的安全性を損なう瑕疵」(最高裁判決)が存在するかどうかによります。
それは、当該瑕疵の性質に鑑み、「これを放置すると、いずれは居住者等の生命、身体、健康、または財産に対する危険が現実化することになる場合」も含まれます。
例えば、①建物の全部または一部の倒壊に至る危険がある場合、②外壁の落下や建物利用者の転落に至る危険がある場合、③漏水、有害物質の発生等により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険がある場合は含まれますが、④建物の美観や居住者の居住環境の快適さを損なうに留まる瑕疵は、これには該当しないとされています。
|
| 5. |
建設業者の責任を問う方法としては、債務不履行責任、瑕疵担保責任を問うにも期間の問題があり、民法709条によれるかどうかが、「瑕疵」の内容によって決まることになります。
|