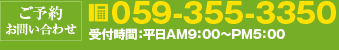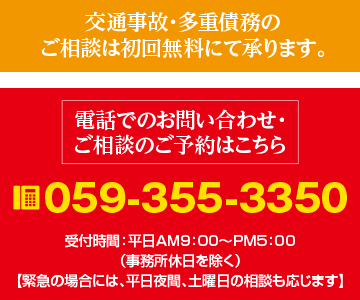|
事業者向け業務

解雇権の濫用
トラブル防止へ新法施行
解雇とは、使用者が一方的に労働契約を将来に向かって終了させるために行う労働者に対する意思表示のことで、いわゆる「くび」です。
解雇は生活に及ぼす影響が大きいため、労働基準法などで個別に禁止されています。
例えば、業務上の傷病による療養の休業期間及びその後の30日間の解雇は禁止されます。
しかし、個別禁止規定に該当しなければ、使用者は自由に従業員を解雇できるかというと、そうではありません。
労働基準法18条の2が新設されました(1月1日施行)。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と言う規定です。
この立法の趣旨は、最高裁判所の判例で確立していた解雇権の濫用法理を法律上明確にすることにより、労使間に十分周知させ、解雇を巡るトラブルの防止と解決をつなげるということです。
ただ、この規定により、企業の行う解雇がこれまで以上に制限されるようになったというわけではありません。
もとより、解雇には客観的で合理的な理由が必要ですので、従業員に「笑顔がない」「不満そうなオーラが出ている」などという主観的な理由では解雇理由にはなりません。
さらに、解雇理由が客観的で合理的なものだとしても、社会通念上相当なものでなければなりませんから、労働者をくびにするほどのものとは評価し得ない場合にも解雇は濫用として無効になります。

「朝日新聞」に掲載された記事です。
|